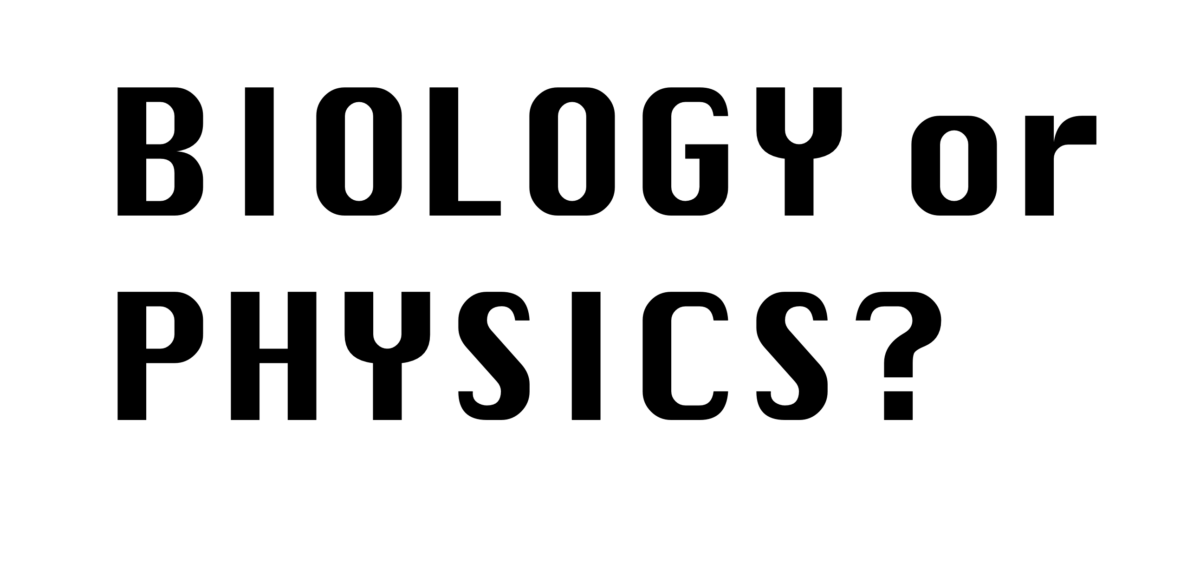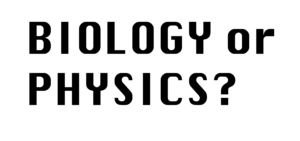「生物と物理、どちらを選択した方が、医学部に受かりやすいですか?」
春先に、生徒からよく受ける質問です。続く言葉が「物理の方が有利なんですよね?入学者には物理選択者が多いし」というのもお約束です。こういう生徒は数字の表面だけを見ている。
医学部入学者の内訳をみると、確かに物理選択者が7〜8割で生物選択者の2〜3割と比べると多いです。一見すると物理が断然に有利、物理一択のように映ります。しかし、物理が有利だから、入学者に物理選択者が多いのではありません。
これにはカラクリがあります。
- そもそも物理選択者の方が多い(60〜70%)
- 物理選択者には数学を得意とする生徒が多い(数学が得意だから物理を選択する)
- 医学部レベルの生物をきちんと教えることができる講師が少ない
というふうに、必然的に物理選択者の合格者数が多くなるわけです。
手元に正確なデータがあるわけではないですが、これまで多くの医進系予備校で教えてきて、確信しています。重要なのは、科目内の合格率(生物選択者あるいは物理選択者内での合格率)の比較ですが、物理の方が少しだけ有利かなという印象です。先ほどの“カラクリ”が効いているのだと思います。統計処理してみると、面白いでしょうね。
ですので、生物選択だからといって、めちゃくちゃ不利かと言うとそんなことはなく、十分に戦える。大学や年度によっては、生物選択の方が有利な場合も当然ある。このへんは、運もありますね。
だから、生物でも物理でも、どちらでも受かります。
では、どちらを選択するか。
科目を選択するうえで、本人の性格や能力、適正が重要という人がいます。不毛です。彼女は物理脳、彼は生物脳ですって。本気で言ってますか。「本人に合っていないことは、やらせてはいけない教」、「得意なことだけ伸ばしましょう財団」の方ですね。人をタイプ分けして、型に嵌めたがる。人間ってそんなに単純でしょうか。
あなたの適正は、鍛えるほど成長し続けます。今日できなかったことが、明日できるようになる。環境(予備校、講師、ライバル)の影響も大きい。覚えるのが苦手?読解力がない?文章が書けない?計算なんか無理?それは、これまでのあなたでしょう。発展途上の自分にレッテルを貼るな。自分で自分の限界を決めるな。
「選べるなら向いていそうな方がいいでしょうよ。時間ないし」という意見はもっともです。ですが、正しい選択肢を選べているかはわかりません。受験生活にリセットボタンはないので、確認のしようがありません。そのことは認識しておかないといけない。
たとえば、英語や数学について考えてみます。いずれも必須科目なので、医学部に行くには、いやでもある程度は習得する必要があります。はじめは苦手だったのに、適正はなかったのに、死ぬほど努力して、講師に質問しまくって、気がついたら得点が伸びた。得意になっていた。いつの間にか好きになっていた。合格した。なんてことは、ふつうです。やったから、変わったわけです。適正、なかったけど、あったじゃん。逃げていたら、そうはならなかった。
適正は、育てられる。
したがって、物理を選ぼうが、生物を選ぼうが、どっちでもいいし、どっちもきついわけです。どちらを選択するかは、直感に任せて、「なんか楽しそうだから、こっちにする」でいい。重要なのはそのあと。選んだ道をどう進むか。
あとで、振り返ったときに、選択が正しかったことにする。これが正解だと思います。
だから、あの質問には、そもそも存在意義がない。そう思いませんか。
結局、決めた科目にどのように取り組むのか、誰に教わるのか。これに尽きます。

ちょっと暑苦しかったですね。さておき。
冒頭の質問をするのは、生物に興味があり、生物を選択したいけれど、怖がっている生徒さんがほとんどです。ですので、私は悩んでいる生徒さんには、数字の話をした上で、「生物が好きなら、興味があるなら、がんばれるなら大丈夫。ぜんぜん受かるよ。」と答えます。
背中を押す理由として・・・
- 合格点を取れる実力をつけさせる自信がある
- 好きな科目は絶対に伸びる
- 医学部入学後の勉強がスムーズになる(細胞学、分子生物学、生化学、解剖学、神経生理学、免疫学などの基礎が身につく)
ことを付け加えます。受験勉強は本当につらいです。少しでも科目に興味を持って楽しく学んでほしい。あと、単純に生物学は本当に面白いですし、生活の役に立ちます。なぜ、高校で必修にしないのか、不思議です。
以上、簡単ですが選択に悩んでいる生徒さんの参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。