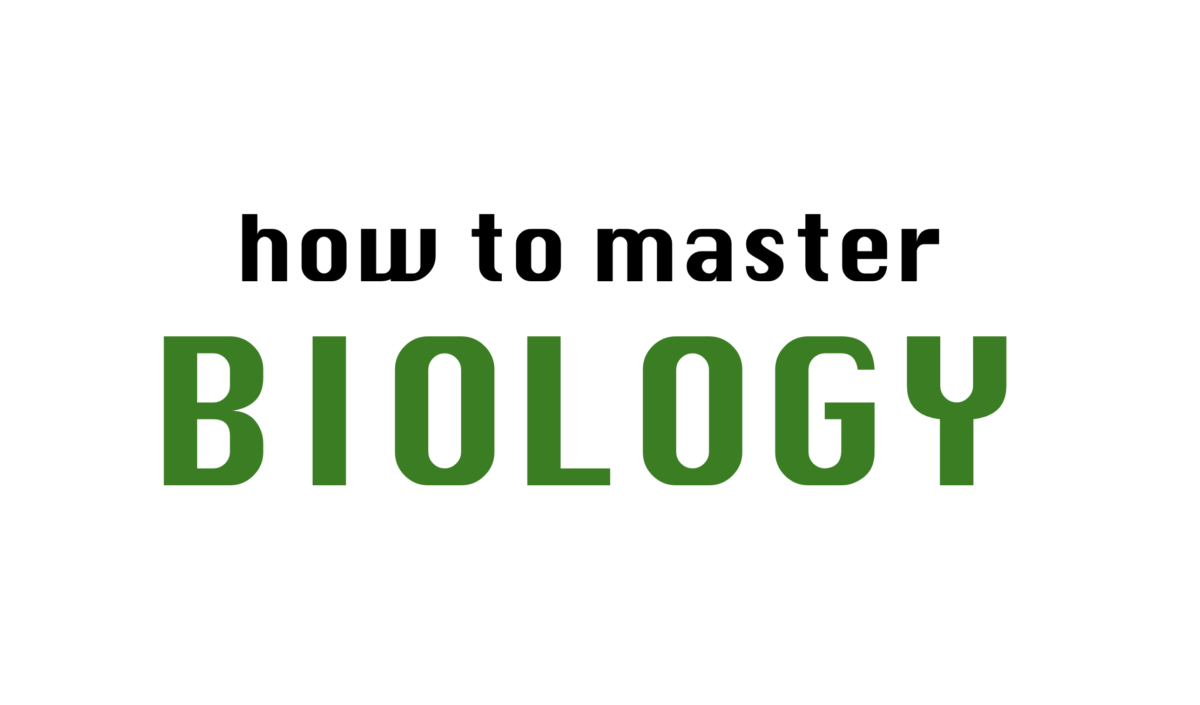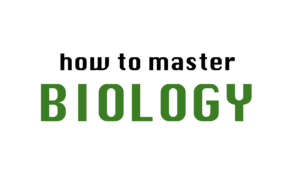試験で得点が取れない勉強法では、どれだけ時間をかけても無意味です。
予備校の授業に出る。講師の話を聞いてノートをとる。宿題に出された問題を解いてみる。次回の授業で解説を聞いて納得した感じになる。がんばったつもりだったのに模試では撃沈。こんな残念な経験はありませんか。
このような落とし穴に落ちてしまうのは、実戦を想定した準備ができていないからです。これでは勉強とは言えません。
以下に当塾の指導の進め方・方針をまとめます。少し長くなりますが、お付き合い下されば幸いです。
まずはインプットです。分野ごとに基本的な知識を身につけます。オリジナルテキストをベースに、登場するワードとその特徴を正確に覚えます。このとき、ワード間のつながりを理屈だてで考えて理解しながら進めます。一番の肝ですから、わかるまで繰り返ししつこく指導します。内容がわかれば覚えられますから。ここで講師の力量(=わかりやすい説明ができるか、生徒を納得させられるか)が問われますが、その点はお任せください。また、ときには今学んでいることが医学にどのように応用されるかを伝え、生徒さんの興味を引き出します。
生物はいわば有機物でできたマシンです。マシンには様々なパーツがあり、パーツが作動する巧妙な仕組みがあり、パーツどうしは密接に連関しながら、全体として調和の取れた動きをします。そのことを常に意識しながら学んでもらうことで、やがて部分から全体までを俯瞰した理解に到達します。
膨大な量のワードを覚える必要がありますが、心配ありません。生徒さんの癖や個性に合わせた記憶術を習得してもらいますので、すぐに覚えるのが楽しくなるはずです。他教科の勉強にも生かせる技を授けます。
次はアウトプットのチェックです。テキストの内容を深く理解するために、医学部の過去問を中心に編集したオリジナル問題集を使い、どこまで覚えられているか、内容を把握できているかをチェックします。初めは苦戦するかもしれませんが、間違えることも記憶を定着させる上で大きな効果があります。めげずに粘り強く前に進むことで着実に実戦力がついていきます。
当塾のオリジナルテキストの内容は、問題集と相互に連動した構成になっています。医学部で想定される出題のヒントや答えを見越し、テキストの流れの中にツッコミどころを“仕込んで”あります。なので、授業を受けている段階で、すでに演習問題で遭遇する実戦的な領域まで踏み込んだ理解が進む。問題を解きながら、「ああ、これは先生が言っていたことじゃん。知ってるし。」と納得しながらこなすことができます。
なお、応用的な問題(計算や実験考察、論述)に関しては、頻出・定番の問題の解法を一通りマスターしてもらいます。私のほうで生徒さんの答案を分析し、どの部分で理解が足りないのか、または誤解が生じているのかを見極めて修正箇所を指摘し、生徒さんと一緒に修正に取り組むことで定着を促します。
目標は、計算問題の場合は、問題にある現象の背景を的確にとらえて内容を見切った解答ができるようになること。実験考察問題の場合は、リード文および実験内容を正確に把握し、実験結果を客観的に分析し、適切な考察と論述ができるようになることです。
問題集を解いたら、復習です。間違ったところを訂正し、正しい理解へと修正するのはもちろん、正解したところも見返し、考え方が合っていたのかをチェックします。これらは質問・連絡として講師にそのまま伝えてもらうことで、正しい理解のすり合わせができます。この作業が理解を強固なものとするためにもっとも重要です。
最後にオリジナルテキストに戻り、内容を再確認します。問題を解き復習したことで新たに気づいたことを、テキストにどんどん書き込んでもらいます。これで自分だけのわかりやすいテキストが出来上がり、内容の多くが定着した状態になります。
上記の復習を繰り返すことで、やがてテキストのどのページのどのあたりに何が書いてあったかを詳細に思い出せるようになります(簡単なテクニックがあるのですが、詳細はここではお話しできません)。つまり、脳にインプットしたテキストの内容をアウトプットできる状態になったわけです。ここまで行ければ完璧で、連動して実戦力が養成され、試験の得点は飛躍的に伸びます。
以上が当塾の指導の進め方・方針です。「そんなうまく進むんかいな?」と思われるかもしれませんが、これまで多くの生徒さんを対象に実践し、合格に導いてきたメソッドです。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。