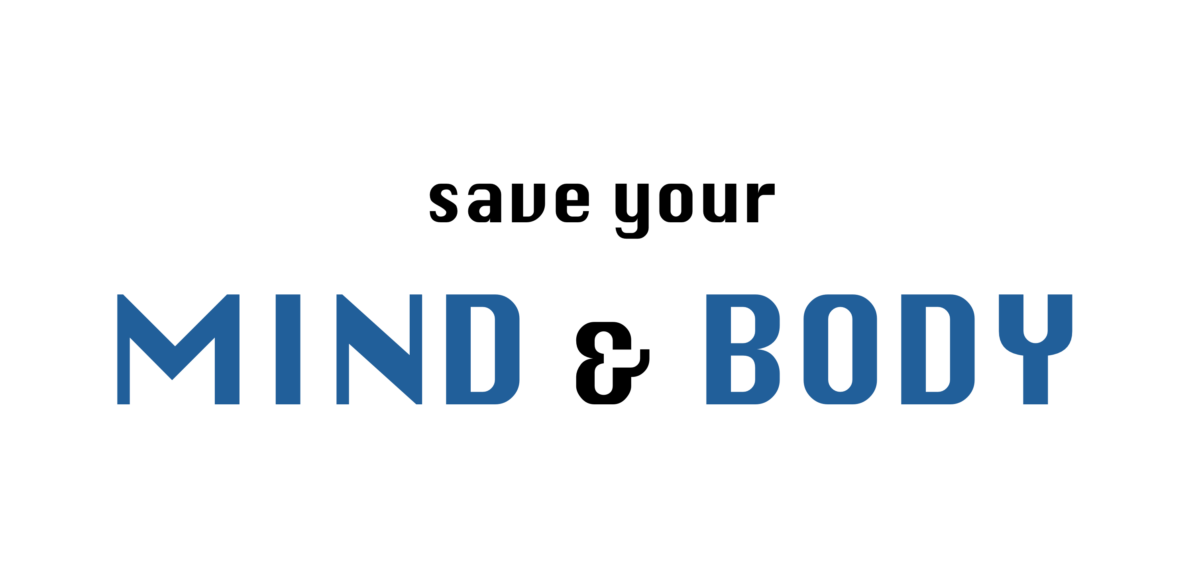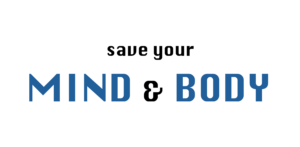受験生活は、ホントにつらい。精神的にも肉体的にも。成績はプレッシャーになるし、肩は凝る。だから、心と体を健康に保つことがとても大切です。それには、体に良い食事や適度な運動、適切な休養などが欠かせません。
今回は心身を整える食事にフォーカスしてご紹介します。食事に気をつけることで学習の成果は格段にアップします。ぜひ最後までお読みください。
受験生にとって、食べることは数少ないリフレッシュの一つです。以下にあげる内容は、決して強要するものではありません。好きな食べ物を楽しみつつ、「少し食べ方を工夫してみてください」というご提案と受け止めてください。
腸がよろこぶ食べ物を摂ろう
「腸?心と体の話じゃないの?」と思われたかもしれません。心と体が互いに関係しているのは自明として、その間に腸が大きく関係していることをご存知でしょうか。以下、超簡単にまとめます。
脳(心)と腸が互いに影響を及ぼし合っていることを「脳腸相関」と言います。たとえば、何らかの精神的なストレスがあると脳から腸へシグナルが送られて腸が敏感に反応し(お腹を壊す)、腸にストレス(病原体の感染など)があるとこれが脳へ伝わり脳の状態が悪化します。逆に、腸の調子が良ければ脳の状態(精神状態や脳機能)も良くなります。
腸は、摂取した食べ物を消化吸収する消化器官であるとともに、口から侵入した病原体から身を守る免疫器官でもあります。腸内には天文学的な数の細菌がすみついています(これを腸内細菌叢または腸内フローラといいます)。いわゆる相利共生です。ヒトは細菌に住処と食べ物を与えます。一方で細菌は腸内の病原体の増殖を抑えるとともに、ヒトの神経系を介して脳に情報を伝えます。この情報が脳の働きにさまざまな影響を及ぼします。まるで脳と細菌たちが繋がって会話をしているようです。なんとも不思議な気分ですが、動物が生まれた太古の時代から続いてきた強力なパートナーシップなのです。
なので、細菌がよろこぶ食べ物を送ってあげると腸内フローラのコンディションが上がり、宿主であるヒトの免疫系や脳のパフォーマンスが上昇します。具体的には風邪を引かなくなる、性格が明るくなる、集中力や記憶力が上がるなど。良いことづくしですね。
では、腸内細菌(もはや腸そのもの)がよろこぶ食べ物、積極的に摂取すべき食べ物、反対に摂取し過ぎない方がよい食べ物とはどのようなものでしょうか。
積極的に摂取すべき食べ物
| 食物繊維を多く含むもの | オートミール、そば、切り干し大根、枝豆、納豆、きのこ類、海藻類 etc |
|---|---|
| 発酵食品 | ヨーグルト、納豆、キムチ、味噌、ソフトチーズ etc |
| ビタミンB1を多く含むもの | 豚肉、うなぎ、納豆、豆類、胡麻 etc |
食物繊維は腸内細菌の餌となります。発酵食品には細菌そのもの(プロバイオティクス)が含まれていますし、腸内細菌の餌にもなります。ビタミンB1は腸内細菌の中で特に重要な役割のある細菌類の増殖に必要です。
摂取し過ぎない方がよい食べ物
| 脂っこいもの | 肉類、フライドポテト、フライドチキン etc |
|---|---|
| タンパク質を多く含むもの | 肉類 etc |
肉類は一度に食べ過ぎると消化しきれずに腐敗が起こり、腸内細菌に悪い影響を及ぼします(お肉を食べ過ぎた後、おならが異様に匂うのはこのためです)。また、高温調理された食品(揚げ物など)も腸内細菌のバランスを崩す要因となります。お肉と同じくタンパク質や脂肪が多いお魚ですが、消化されやすく、お魚に含まれる脂肪(DHAやEPA)は体に良いので、積極的に食べましょう。
手軽さで行くと、納豆とヨーグルトがおすすめです。これらは毎日摂取したいですね。お肉は食べすぎに注意しましょう。腸内フローラのコンディションの向上は、便通や肌の状態がよくなることで実感できます。
脳が疲れたと感じたら
受験生は毎日脳をフルに稼働させます。「頭が疲れた」、「頭が重い」、「何だか集中できない」という場合は、脳の活動に必要な直接のエネルギー源であるグルコース(ブドウ糖)を摂取するとよいです。
白米やパンなど炭水化物を多く含む食品の摂取も良いですが、これらは消化された後でグルコースとなるため、即効性に欠けます。グルコースそのものを多く含む、ラムネやはちみつをおすすめします。授業の合間にラムネをポリポリやったり、紅茶にはちみつを入れるとかは簡単にできますね。
高タンパク質食材が脳を育てる
勉強をいくらがんばっても、脳に適切な栄養が届けられていないと成果は半減します。脳を構成するニューロン(神経細胞)は、刺激を受けると細胞同士が新たなシナプスを形成し、複雑なネットワークを構築します。ネットワークが複雑であるほど、記憶など脳機能は強固なものになります。なので、ニューロンがシナプスを形成しやすいように、材料を与えてあげる必要があります。
材料の一番手はアミノ酸なので、タンパク質(アミノ酸をモノマーとするポリマー)を多く摂取することをおすすめします。卵やお肉、お魚が該当します。とはいえ、前述したようにお肉の摂取量には注意する必要があります。なので、朝昼晩と3食にわけて、卵やお肉、お魚をバランスよく適量を摂取するようにすると良いでしょう。特に、朝食にタンパク質を摂ることを忘れないでください。
いかがだったでしょうか。以上、受験生の心身を整えるメソッド【食事編】でした。今回の記事がご参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。